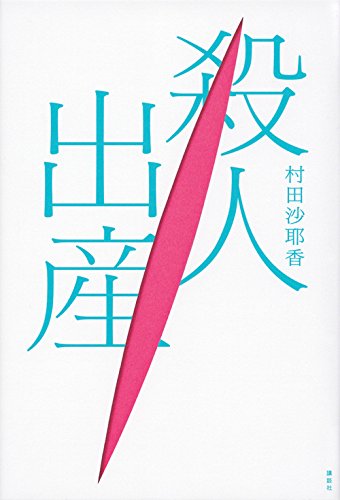空気について。もしくは、蝉スナックとかさ…
きょう発売の「週刊現代」の書評頁「人生最高の10冊」で、山崎ナオコーラさんの記事を担当しました。
タイトルが仰々しくて、取材のお願いをするときに、いつもためらいます。そんなたいそうなものは、と断られたりもしましたし。
「作家になってからの友人の本をあげたいのですが、いいですか」
今回そんなふうに逆提案されたのは山崎さんが初めてでした。絞るにしてもミステリーに 限ってとか、青春時代とか限定をつけられることはあっても「友だち」というくくりは、新鮮でした。理由は、文学はそれでもなくとも売れない。みんなで盛り上げなくちゃ、というのも、言われてみたらなるほど。
柴崎友香さん、西加奈子さん、島本理生さん、といった同年代の作品をあげられたなかで、村田沙耶香さんの『マウス』(講談社文庫)がはいっていて、これがワタシ的にはけっこうハマリました。
小学校の5年生のクラスでのデキゴトから大人へ成長していき……と綴られていく長編小説で、主人公の律(りつ)という女の子は、目立たないよう、波風をたたせないように、いつも教室の隅っこで身をひそめている。ジミな女子。
教室の中心に陣取るボス格の女子グループがいて、さらにひとり、ものすごく目立つ女の子がいる。瀬里奈というその子は無口で、何を考えているのかわからない。ぽつんとしていて、何かあると、大声で泣いて止まらなくなる。
ああーまた泣いちゃったよ、とイジメの対象になったりしている。主人公の律は、その子が気になって……という話。ある日あることがきっかけで、嫌われたものだったその瀬里奈が豹変し、主人公をも変えていくという展開で、本人が変わることで周囲の見方、接し方が、がらがらっと逆転。一度変わってしまえば、まるで昔からそうだったかのように周りも歩調をあわせ空気をこしらえていく。そういう感じが、よく出ていて、多少無理のある設定とかあるものの、面白いなぁと思った。
まあ、そんなこともあって、村田さんの新刊書も読んでみた。『殺人出産』(講談社)。オビに「10人産めば、1人殺してもいい。」とある。
いまから約百年後が舞台で、人口減少に苦慮した政府がトンデモな対策を打ち出し、それが定着しつつあるという設定。個人による殺人を条件付で政府が認める、つまり殺人を合法化してしまうというのもすごい話。
科学の進歩で、男も人体を改造され出産が可能となっている。それも驚きだが、人工授精が一般化し、ふつうにセックスをして子供が生まれるというのはごく稀な出産となっている、それくらい世の中は変化した社会でのデキゴトだ。
ギョッとしたということでいうと、そういう出産がどうしたこうしたという話以上に、セミとかトンボをスナック菓子として若者が食するのがブームになっていて、ポテトフライを食うようにして口にしている情景に、どんびきしてしまった。昆虫だめなんですよ。
まあ、マックで「蝉スナック」をポリポリってやっている。いまだと考えられないけれども、百年後にはみんなふつうに口にしているよというわけだ。まわりの誰も、トンボをぼりぼりやっていても、おかしいという目で見たりしない。それくらい世の中のモノサシも違っているということ。
怖いなぁ、と思ったのは、いまのワタシたちからするとイジョーに思えることが、そこではみんな、多少おかしいとか思うひとがいても、蝉スナックのように一度当たり前という空気ができあがると、おかしいと口にするひとが社会から消えてしまっていること。
いや、いることはいて。それは蝉スナックを食べながらも、いまの殺人出産制度はおかしいとレジスタンス的に活動するひとがいる。
ただ、そういうふうなひとたちは、ここでは「変わったひと」「危険でオカシなひと」として扱われる。
うまいなぁと思ったのは、レジスタンスのひとが言うことは正論なのに、うざいなぁと、読者であるワタシですら主人公に同調して、遠ざかりたい気分になっていることだ。
殺される対象に指名されたひとを社会では「死に人」と呼び、敬うというのか、葬儀の場で遺族に「ありがとう」とお礼をみんなが口にする。社会のために貢献してくれた、犠牲になってくれたという気持ちを込めたことばになるのだが、いまの尺度だと考えられない。
ここから連想したのは、ニッポンが戦争していた時代に、出征兵士を送り出すニュース映像だ。沿道に人だかりができ、白い割烹着の女のひとたちが小旗を振って、祝っている。
「死に人」に指名されたひとは、逃げられない。なんせ国家プロジェクト。監視と追跡から逃れるすべはなく、逃げてもすぐに捕らえられてしまう。
そうそう。最初はなんとなくスルーして読んでいたが、10人を産むということは、合法的に殺人の権利を獲得するまでに10年を要するということ。つまり、十年間、産むための施設に半ば隔離され、変わることなく殺意を抱き続けた末にその権利を得るということ。肉体的にもきつく、途中で亡くなるひともいて、だから権利を獲得したひとを社会は祝福する。
誇張した社会の物語ではあるけど、それほどにまで殺したいと思う気持ちとはなんだろうというふうに思考がスリップしはじめる。
たとえば、何かの復讐のためにというのはわかる。しかし、この小説が斬新なのは、そういうわかりよいものばかりではない。なんとなく、誰でもいいから殺したい。
そんな動機をもつひとがあらわれるようになった近未来というのが、この小説のすごみだ。つい先日の事件、友人を殺害した少女が供述したハナシを事前に予見していたかのようでもある。
ハナシはすこし逸れる。「テンチャン」
テレビに映るたび、うちの父親は昭和天皇をそう呼んでいた。もちろん父が軍隊にいたころは、一言でもそんなことを口にしたらとんでもないことになっていたはずだ。
「みんな陰ではな、テンチャンていうてたんやで」
と父は負けん気つよく言い返していたが。
祖父はというと、ワタシが幼いころ、旗日には必ず日の丸を門柱に立て、毎朝、東を向いて手をあわせる。いつも着物に帯をしめ、明治を体現するようなひとだった。
大正生まれの父がリベラルな思考をしていたのは、おそらく祖父への反発も作用していたのではなかったかとワタシは思っている。あるとき神様でもあった「陛下」が、ある日を境にして「テンチャン」と呼ばれる。いい悪いではなく、それは激変というよりも、なだらかなグラデーションのようにして空気が変わり、その空気によって、呼称もまた変わったということなのではないか。
先日アントニオ猪木さんが訪朝し、プロレスの親善イベントを開催するというのに絡めて、北朝鮮がどんなにトンデモ国家かというのを、コントを見せるかのように、ニュース番組が紹介していた。
とりわけ目新しいものがあったわけではない。若い坊ちゃん刈りの指導者に、壮年の幹部たちがぺこぺことへつらっているのも、大袈裟に感動を身体で表現するのも、お得意の一糸乱れぬ行進も。見るたび、既視感に襲われる。
運動会のたびに、小学校でこういうのをやらされたよなぁと。もちろん、おかしいとか考えもしなかった。
笑ってもいいものか。リーダーがこうと決めたらおべんちゃらを口にするのも、宴会で太鼓もちを装うのも、似たようなもの。極端に戯画化しただけで、苦笑はすれども、哄笑はできない。
もういちど『殺人出産』にハナシをもどすと、設定はとっぴではあるが、終始既視感にとらわれながら読んだ。たとえば『時計じかけのオレンジ』を観たあとの、ざらざらとしたあの感覚にちかい。
軽快なタップの音楽にあわせ、コミカルな身振りで若者が老人に暴行を加える。遠い未来を描きながらも、少年たちによるホームレス殺人が多発するまでにそんなに時間はかからなかった。
なってほしくない、いやな予感ほどよくあたる。
脱線ついでに、最近のニュースで、気にかかったのが二つある。
ひとつは、福島の原発事故で避難していた女性が自殺し、遺族が東京電力を訴えた件。先日の福島地裁の判決は、東電の責任を認める画期的なもの、血の通うものだったが、被告である東電が反論にあげていた論旨が、いまの社会を映し出していると思った。
女性は、もともと精神的に弱かったから自殺に至った。自殺と原発事故には因果関係はないということを立証するために、自殺したひとは弱かった、弱いものはまるでこの世に生きる資格はないかのように聞こえるものだった。
幸い、判決は東電のそうした主張を退けたものの、こうしたまっとうと思える判決が覆られる、そういうことにおかしいと思わぬ空気がもしつくられでもしているようだと……。そうならないことを願うが。
気にかかったもうひとつは、盲導犬を何者かがフォークみたいなもので突き刺したという事件。犯人像がどうとかということよりも、電車から降りコンビニを経由して職場についてはじめて、飼い主は犬が怪我させられていたことを知ったという。盲導犬は、吠えないよう、人間に敵意を示さないように躾けられているために、気づかなかったという。
陰鬱な気持ちになったのは、その犯人がどうであれ、その現場でなくとも、途中で盲導犬の怪我に気づくひとはいなかったのだろうか。盲導犬がいれば、ふつうはなんとなくそちらに視線がゆくものだ。そして怪我をしていれば「ワンチャン、怪我してしますよ」と一声かけるくらいするほうが自然だと、ワタシは想像する。
誰ともすれちがうことなく、飼い主は移動していったというか。誰からも声をかけられなかったというのはどういうことなのか。
月に何度か、犬に悪さをされる。盲導犬が黙っているものだから、帰宅してはじめて、犬の額に落書きをされていることを知ったりすることもあるという。大事なパートナーが危害を加えられている、その場に居合わせながら、目が見えないばかりにそのことに気づかないでいるということがどんなにそのひとを苦しめるか、暴行を加えた人間も、それを眺めていた人間も、想像を働かせはしないのだろうか。想像した結果なのか。
それが、なんとなくできあがりつつある今の空気がもたらすものだとしたら、厄介だと思わずにいられない。